旅の3日目昼食後、五所川原の立佞武多館見学。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
高さ23m、7階建の高さです。上から下まで姿全部おさめるの大変。
五所川原のねぷた祭りは、毎年新たに作られたのと過去2年間の3基が市中巡るそう。その保管も兼ね展示されてる建物です。建物側面が大きく横にスライドして幕があく。高さ23m 幅6m 重さ19トンの巨大ねぷたが出陣する仕掛け。迫力あるだろな〜
![]()
エレベーターで4階まで上がり螺旋スロープ降りながら見学。
上にあがるとやっと奥のかぐや姫の顔見える。
![]() エレベーターの中からも、第22代「かぐや」に興味津々
エレベーターの中からも、第22代「かぐや」に興味津々
![]()
![]()
勇壮な武者姿ではなく女性が描かれるのは珍しいし、涙流してる姿ってまず無いそうですよ。
![]()
![]()
スロープ壁の展示では
![]()
![]()
![]() 東日本大震災の2011年と翌年のテーマ何かと目を凝らす。構想から完成お披露目まで1年かかります。
東日本大震災の2011年と翌年のテーマ何かと目を凝らす。構想から完成お披露目まで1年かかります。
![]()
吉幾三さん、ヤテマレ!と威勢よく楽しく歌われてます。
![]()
台座の漢雲ってなんだろうと思ってた。
漢字は右から読むので「雲漢」天の川のことだった。
奈良時代に中国から伝わった七夕祭りが起源ともいわれ、津軽の習俗と精霊送りなどが一体化。川や海に流して無病息災を祈る灯籠が、ねぷたの原型になったと考えられるそう。
「ヤーヤドー」弘前城ねぷたと、「ラッセラー、ラッセラー」青森ねぶた
![]()
享保7(1722)年初めて文献に登場して300年!表には勇壮な三国志や水滸伝などの武者絵が描かれ、背面には妖艶な美人絵が多く描かれる。
明治時代の立佞武多。![]()
町に電線が敷かれるようになると運行妨げられ、巨大な立佞武多は廃れて小型なものに。1993年五所川原の豪商「布嘉」に仕えていた大工の遺した、巨大ねぷたの設計図と思われる図面が発見されたのをきっかけに80年の歳月を経て、巨大ねぷた復活。
一度きりのはずが、多くの市民の要望もあり市が正式にねぷたの復活を決定。電線などが地中に埋められるなどのインフラが整い、1998年8月5日、高さ22メートル、重さ16トンにもなる巨大ねぷた「立佞武多」と命名された巨大な人形灯籠「親子の旅立ち」が町を練り歩いた。
「五所川原立佞武多」は、「じょっぱり」で「もつけ」な人々の存在論的証明なのである。
詳しくは👇![五所川原立佞武多 | JAPAN WEB MAGAZINE]()
他に目に留まったものは
![]() 茨木童子と渡辺綱
茨木童子と渡辺綱
![]() 売店で、金魚ねぷた
売店で、金魚ねぷた
![]()
出口で見たポスター、2021/10/9
第22代「かぐや」が初めていざ出陣したのは令和元年(2019)7月19日だった。
![]()





高さ23m、7階建の高さです。上から下まで姿全部おさめるの大変。
五所川原のねぷた祭りは、毎年新たに作られたのと過去2年間の3基が市中巡るそう。その保管も兼ね展示されてる建物です。建物側面が大きく横にスライドして幕があく。高さ23m 幅6m 重さ19トンの巨大ねぷたが出陣する仕掛け。迫力あるだろな〜

エレベーターで4階まで上がり螺旋スロープ降りながら見学。
上にあがるとやっと奥のかぐや姫の顔見える。
 エレベーターの中からも、第22代「かぐや」に興味津々
エレベーターの中からも、第22代「かぐや」に興味津々

勇壮な武者姿ではなく女性が描かれるのは珍しいし、涙流してる姿ってまず無いそうですよ。


スロープ壁の展示では
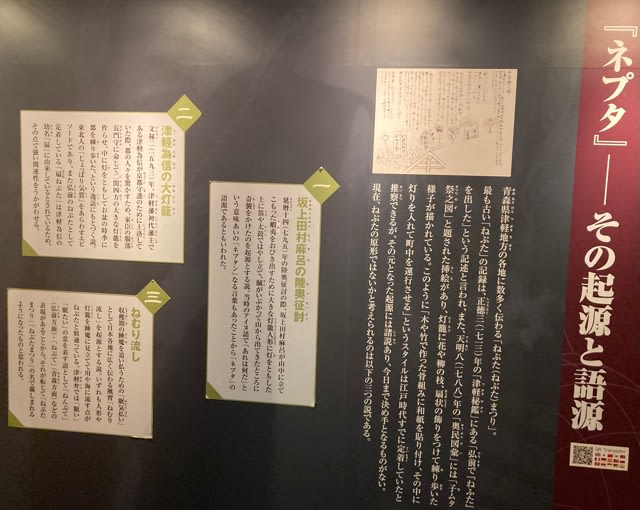

 東日本大震災の2011年と翌年のテーマ何かと目を凝らす。構想から完成お披露目まで1年かかります。
東日本大震災の2011年と翌年のテーマ何かと目を凝らす。構想から完成お披露目まで1年かかります。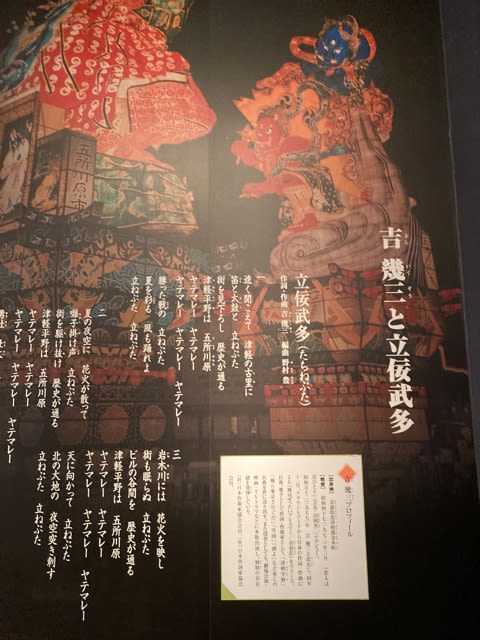
吉幾三さん、ヤテマレ!と威勢よく楽しく歌われてます。

台座の漢雲ってなんだろうと思ってた。
漢字は右から読むので「雲漢」天の川のことだった。
奈良時代に中国から伝わった七夕祭りが起源ともいわれ、津軽の習俗と精霊送りなどが一体化。川や海に流して無病息災を祈る灯籠が、ねぷたの原型になったと考えられるそう。
「ヤーヤドー」弘前城ねぷたと、「ラッセラー、ラッセラー」青森ねぶた

享保7(1722)年初めて文献に登場して300年!表には勇壮な三国志や水滸伝などの武者絵が描かれ、背面には妖艶な美人絵が多く描かれる。
明治時代の立佞武多。

町に電線が敷かれるようになると運行妨げられ、巨大な立佞武多は廃れて小型なものに。1993年五所川原の豪商「布嘉」に仕えていた大工の遺した、巨大ねぷたの設計図と思われる図面が発見されたのをきっかけに80年の歳月を経て、巨大ねぷた復活。
一度きりのはずが、多くの市民の要望もあり市が正式にねぷたの復活を決定。電線などが地中に埋められるなどのインフラが整い、1998年8月5日、高さ22メートル、重さ16トンにもなる巨大ねぷた「立佞武多」と命名された巨大な人形灯籠「親子の旅立ち」が町を練り歩いた。
「五所川原立佞武多」は、「じょっぱり」で「もつけ」な人々の存在論的証明なのである。
詳しくは👇

五所川原立佞武多 | JAPAN WEB MAGAZINE
光の巨像 曲がり角から突然姿を現すそれは、街灯よりもなお高く、まさに見上げるような威容を誇っている。そう、それ
他に目に留まったものは
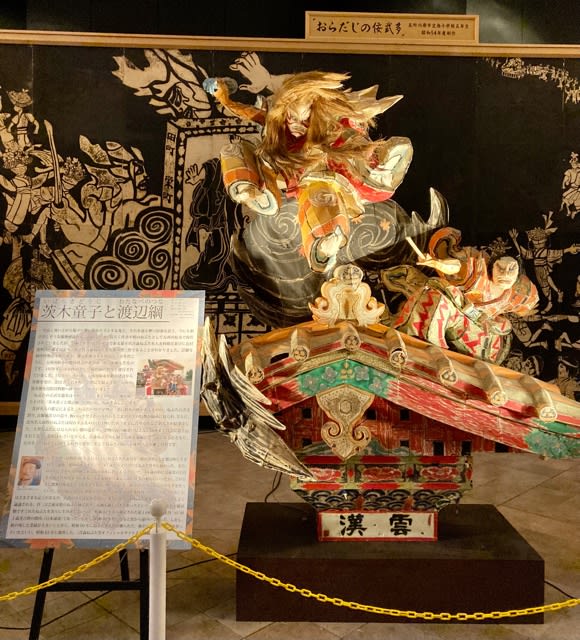 茨木童子と渡辺綱
茨木童子と渡辺綱 売店で、金魚ねぷた
売店で、金魚ねぷた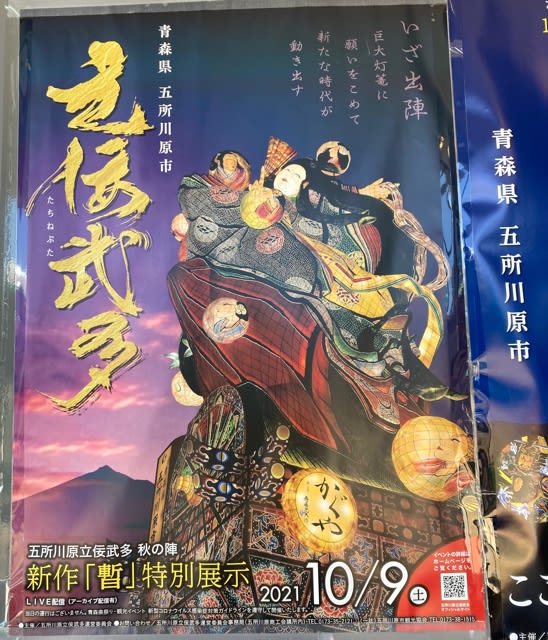
出口で見たポスター、2021/10/9
第22代「かぐや」が初めていざ出陣したのは令和元年(2019)7月19日だった。
